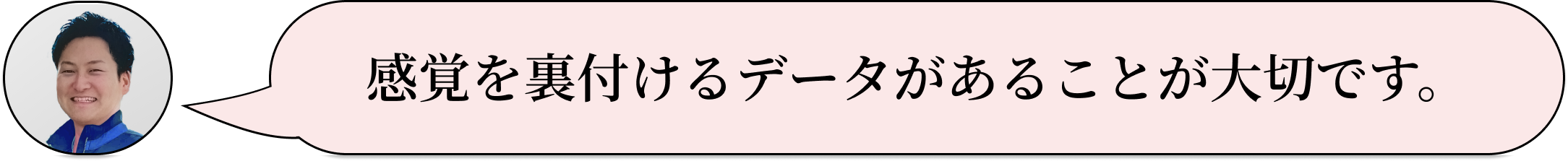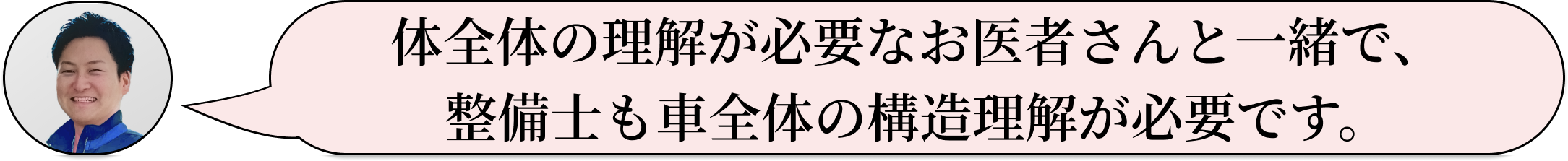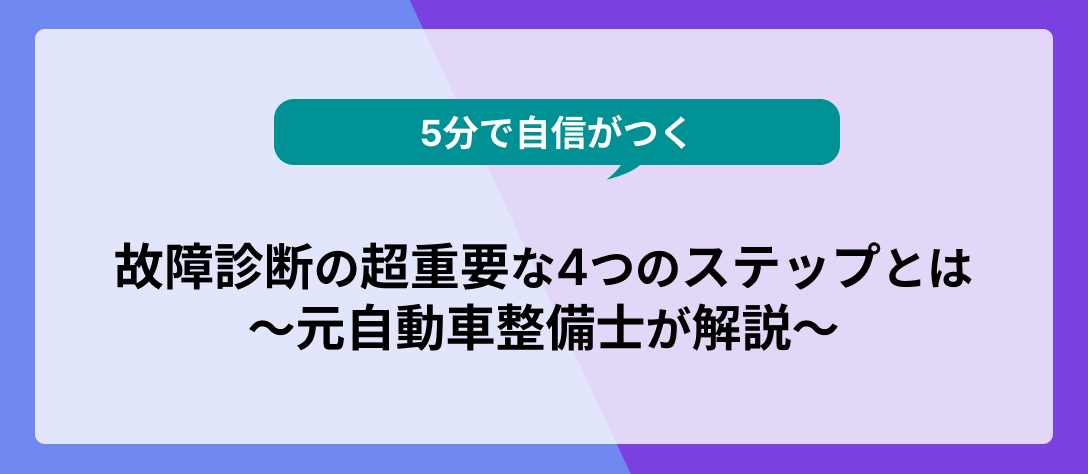
【5分で自信がつく】故障診断の超重要な4つのステップとは~元自動車整備士が解説!~
整備士として工場に就職して数年経つと、故障診断の業務を任されることも増えてきますよね。
とはいえ、「どこから手を付ければいいのか分からない」「ベテランの先輩たちみたいに的確に診断できる自信がない」と悩む方も多いはず。
実際、何十年も経験を積んだ整備士でも、「最近の車はシステムが複雑で、追いつくのがやっとだよ」という声が聞こえることも。
ですが、大丈夫!どんなに高度な技術が求められる分野でも、基本のポイントを押さえれば確実にステップアップできます。
この記事では、故障診断に自信を持ちたいあなたに向けて、診断のコツや押さえておきたいポイントをお伝えします。
これを読んで、一歩ずつ着実に成長していきましょう!
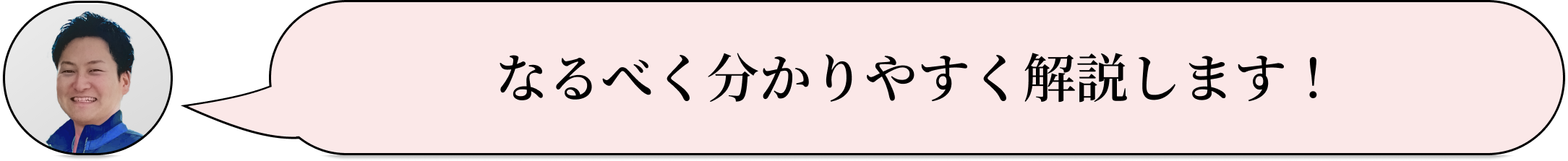

故障診断の進め方

故障診断は、以下の4つのステップを意識することで効率的に進めることができます。
1. 症状や故障内容のヒアリング
診断の第一歩は、お客様から症状や故障内容を正確に聞き出すことです。次に挙げるポイントをもとにヒアリングを進めましょう。
いつから
症状が発生したタイミングを把握することで、トラブルのきっかけとなった可能性のあるイベントや条件を特定する手助けになります。例えば、「1週間前にタイヤ交換をした後から音がする」といった具体的な時期の特定が、点検の方向性を絞り込む重要な材料となります。
また、症状の発生時期がわかれば、関連する部品の使用頻度や経年劣化などの条件を考慮に入れた分析が可能です。
何をすると
特定の操作や行動で症状が出る場合、それが直接的な原因のヒントになります。
例えば、「急ブレーキをかけると異音がする」といった場合は、ブレーキパッドやディスクローターが問題の可能性があります。
操作と症状の関係性を突き止めることで、関与する部品やシステムを効率的に特定できます。
どんな状況で
症状がどのような条件下で発生するのかを確認することは非常に重要です。例えば、
・走行中か停止中か?
走行中と停止中だと各部品への負荷のかかり方や動き方の違いがあるため、関連する箇所を絞り込めます。
・エアコンの使用状況
エアコンをオンにしたときに症状が出る場合、コンプレッサーや電装系、エンジン負荷の増加が関与している可能性が高まります。
・気温や気候
高温や寒冷条件が影響する場合、ゴム部品やバッテリーなど、環境要因に敏感な箇所に注目する必要があります。
症状
症状そのものを具体的に聞き出すことは、問題解決の鍵となります。
「エンジンから異音がする」という場合、
・音の種類(カタカタ、ガラガラ、キュルキュルなど)。
・発生タイミング(冷間時、加速時、減速時など)。
・発生場所(エンジンルーム、タイヤ付近など)。
こうした詳細な情報があれば、点検の方向性を明確にできます。
上記の4つを特に意識してヒアリングし、「事実を集める」ことが大切です。
本来は故障の原因であるにも関わらず、お客様が「故障とは無関係」と判断してしまっているものの特定にも役立ちます。
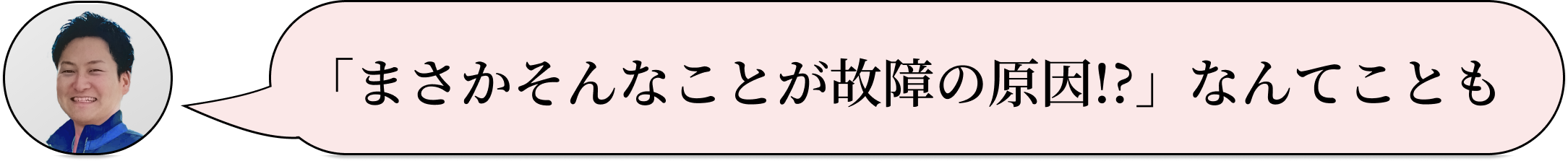
2. 仮説を立てる
ヒアリングした内容をもとに、故障の原因について具体的な仮説を立てます。以下に、実際に起こり得る具体的な例を挙げながら仮説立ての流れを説明します。
「2週間前からエアコンを起動したときに異音がする」場合
仮説:エアコンコンプレッサーのベアリング不良、またはベルトの緩みや劣化。
検証方法:エンジンをアイドリング状態でエアコンをオン・オフに切り替え、異音が消えるかを確認。次に、ベルトの状態やテンションを点検し、異常があれば調整や交換を実施。
「信号待ちで停止した時に車体の振動を感じる」場合
仮説:エンジンマウントの劣化、またはアイドリング制御バルブの汚れ。
検証方法:エンジンマウントの物理的な損傷や劣化を確認。スキャンツールを使用してアイドリング時のエアフローや燃料噴射量を計測し、異常値がないかをチェック。
「加速中に金属が擦れるような音がする」場合
仮説:排気系の遮熱板の緩み、または排気管内のカーボン堆積による共振。
検証方法:車両をジャッキアップし、遮熱板の固定状況を目視および触診で確認。排気ガスの流量やバックプレッシャーを計測し、詰まりがないかを確認。
複数の可能性を視野に入れながら、仮説を具体化していくことで、点検の精度を高めることができます。
3. 点検を行う
仮説をもとに、必要な点検を実施します。たとえば、
・計測機器を活用して電装系や駆動系を確認
・部品の摩耗や劣化を目視および触診で確認
・状況に応じて部品の取り外しや分解を行い、詳細な状態を確認
これらの点検結果を基に、仮説が正しいかを検証し、原因を特定します。
4. 必要に応じてプロセスを繰り返す
もし点検結果から原因が特定できない場合は、再度ヒアリングや仮説立てに戻り、別の視点から再検証を行います。
故障診断は一度で全てが解決するとは限りません。柔軟な発想でアプローチを続けることが重要です。
症状の発生時期や、その瞬間をヒアリングすることで、その前後の出来事から原因を推測します。
診断を成功に導くための意識ポイント
過去の事例に頼りすぎない

過去の経験や事例は大いに参考になりますが、それだけに頼るのは危険です。
例えば、以前の修理で特定の部品を交換して解決したケースがあったとしても、今回は異なる原因である可能性があります。一つひとつの確認を怠らず、地道な作業を心がけましょう。
スキャンツールやテスターを使いこなす

スキャンツールやテスターは、診断の精度を高めるための頼れる味方です。これらの計測機器を正しく使い、数値に基づいた科学的な診断を行いましょう。
「感覚的な判断」ではなく、データで裏付けを取ることで、自分の診断に自信を持てるようになります。
全体のシステムを理解する

「木を見て森を見ず」という言葉がありますが、故障診断でも全体のシステムを俯瞰する視点が重要です。
部品一つひとつが、車全体のシステムの中でどのような役割を果たしているのか。その部品が正常に作動しないと、システム全体にどんな影響が出るのか。
こうした全体像を常に意識することで、不具合の原因をより的確に突き止める力が養われます。
信頼を積み重ねるために作業は確実かつ丁寧に

故障箇所を特定しても、分解・交換作業が雑だと台無しです。納車後に同じ不具合が再発すれば、お客様の信頼を失いかねません。
作業後は何度も確認し、ダブルチェックを徹底しましょう。作業の精度を高めるためには、以下の要点を押さえることが重要です。
・部品が正しく取り付けられているか。
・配線や接続が確実かつ安全であるか。
・動作確認を行い、異常がないことを確認する。
・必要に応じて、同僚や先輩に再チェックを依頼する。
確実な作業こそ、整備士としての信用を築く一歩です。
まとめ 故障診断は経験と学びの積み重ね
いかがでしたか?
故障診断においては、一つひとつの作業を丁寧に行いながら、経験を積むことが何よりも大切です。
迷ったときには、頼りになる同業者や先輩に相談してみましょう。専門家のアドバイスは、時に大きなヒントを与えてくれるものです。
技術を磨きながら、プロフェッショナルとしての道を一緒に歩んでいきましょう!あなたの成長を応援しています。
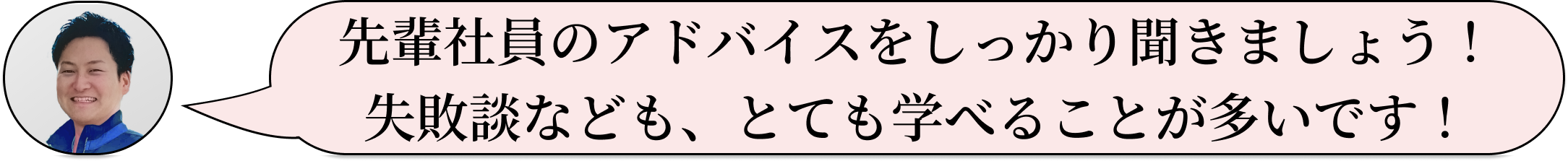
そして、
・さらに自動車整備士のスキルを高めたい
・実戦経験を積んでスキルを身に着け活躍したい
・誰よりも稼ぎたい!
・とにかく整備をして、お金を稼ぎたい
という方は、ぜひ当社の副業サービス「U-match」がおすすめです!
選ばれ続けて、実績15,000件以上!
登録料無料で、お休みの日や空いた時間にしっかり稼ぐことができます。
詳しくは、下のバナーから公式HPをチェック!
毎月600件以上の新着求人、掲載件数は15,000件以上!
全国の整備工場との独自ネットワークを活用し、整備士を中心とした自動車業界の幅広い職種の求人を掲載。
国内最大級の豊富な求人数で、職種や勤務地、工具貸し出しの有無などでの検索も可能。
また、全ての求人に写真が掲載されており、職場の雰囲気も分かりやすい!
整備士や鈑金塗装、営業など自動車業界で働きたい方のための転職求人サイトカーワクなら、理想の職場がきっと見つかります。